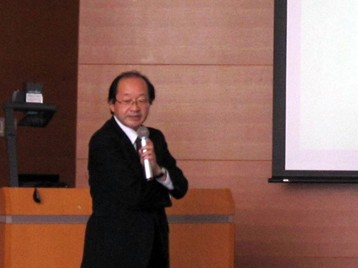menu
ニュース & トピックス
2010年度のニュース
第7回名古屋大学 施設マネジメント研究会議事録(要約版)
テーマ:キャンパスマスタープランとファシリティマネジメント
日時:2010年5月12日(水)13:00 ~ 17:00
会場:名古屋大学IB電子情報館
来場者:340名
研究会 13:00~15:00
開会挨拶:藤井良一(名古屋大学理事・副総長)
キャンパスマスタープランは大学の活動の根幹をなす。大学憲章に則って、30年後のビジョンを示すフレームワークプラン、中期6年のアクションプランをつくり、ファシリティマネジメントの手法を重視して、具体的な実行の方策の提唱も試みている。文部科学省の指導も仰ぎながら、各方面との共通理解を深め、キャンパスマスタープランの在り方、プランをプランとして終わらせずに実行に移す方策について議論したい。
藤井良一(名古屋大学理事・副総長)
趣旨説明 谷口元(名古屋大学 施設計画推進室室長 教授)
ファシリティマネジメント(FM)に関する調査研究、産学官の地域連携としてFMのモデルの構築、ファシリティマネージャーの育成が名古屋大学FM研究会の目的。学内構成員の合意をとって共有したというプロセス、30年後を見据えた6カ年計画を繰り返して実行していくエンジンがFMであり、これが研究会の趣旨に連動している。
谷口元(名古屋大学 施設計画推進室室長 教授)
講演1 「戦略的なキャンパスマスタープランづくりの手引き」
山崎雅男(文部科学省文教施設企画部計画課 整備計画室長)
1.キャンパス整備を巡る現状と課題:多様化と機能別分化を促進して大学の強みを伸ばしていく方が良い。国立大学が法人化し、民間的発想のマネジメント手法など取り入れていく流れが強い。老朽化に耐震化は追いついておらず設備も耐用年数を超えている部分がある。
2.施設整備5カ年計画 : 国の財政状況が厳しい中で計画的な整備をしないと予算確保ができない。国は、キャンパス計画モデルの提示、マネジメントを進めるためのベンチマーキング指標の検討、多様な財源の活用、人材育成などをしなくてはいけない。重点的事項として、3S(safety安心安全、sustainability環境配慮がベーシックにあり、その上にstrategy戦略)。
3.なぜ今マスタープランか?:キャンパスの目指すべき姿、機能別分化、ネットワークの構築を視野に入れ、建物を良くするだけでなく教育研究を活性化するよう、リンクした形で重点施策を定め、マスタープランを作ること。学外に対しては、投資してみようと思わせるように提示できる。学内にもPRし施設マネジメントにつなげていく。
4.マスタープランづくり:アカデミックプラン、経営戦略、現状把握をミックスして、基本方針、整備方針、部門別計画へと進む。それを絵に描いた餅にしないためのアクションプランが重要。計画を作ってPDCAサイクルでまわしていく。検証しながら成長していく。
5.海外の大学:ミシガン大学などの海外の事例の紹介。大学キャンパスの施設配置は活動を具現化している。配置が活動、教育研究の活性化につながるように。
山崎雅男(文部科学省文教施設企画部計画課 整備計画室長)
講演2-1「名古屋大学キャンパスマスタープラン2010について(計画編)」
恒川和久(名古屋大学 工学部施設計画推進室講師)
キャンパスマスタープランは過去に3回作成。不変的に継承すべきものに蓄積を重ね進化を続けている。今回の2010は総合的、かつ実践的。
1.基本目標「世界屈指の知的成果を産み出すエコキャンパス」:コンセプトとして4つの柱「地球環境に配慮した低炭素エコキャンパス/グローバル&ローカルに多様な連携を支援するキャンパス/自由闊達な教育研究風土の基盤となるキャンパス/キャンパスの持続的発展を支え大学経営に貢献するファシリティマネジメント」を立てた。
2.キャンパスの点検・評価と課題:31m以下の高度地区指定を受けた既存不適格の建物、緑地率45%の風致地区への対応、旧核研跡地の利用、耐震化のみの内部の整備、プロジェクトスペースの不足とプレハブの増加、部局別の分散配置、老朽化と狭隘化、CO2排出、全学利用施設の有効活用などが課題。
3.キャンパス・フレームワークプラン~30年後の長期ビジョン:各キャンパスの位置づけ、ゾーニング、将来規模を過剰にしすぎず目標を設定する。3つのコンセプトに対応して交通・エネルギー・資源・緑地・キャンパス利用の方針・機能ゾーニングなどの30年後の姿を見る。その基盤として土地利用の仕方、デザインガイドライン、ユニバーサルデザイン、サイン計画など。
4.6年間のアクションプラン:様々な項目でアクションプランを決め、6年間で何ができるかをポートフォリオにしようとしている。教育研究施設の整備計画では、3つのコンセプトに対応している。例として、省エネ、環境負荷低減アクションプラン。2014年に2005年比20%削減という目標を立てている。
「駅そば生活圏」という「2050なごや環境戦略」のモデルに大学群がなっていくことを、自治体、企業、大学間で考えていきたい。施設マネジメントコンソーシアムを作って教育研究、地域貢献にみんなで取り組める形を整えたい。
恒川和久(名古屋大学 工学部施設計画推進室講師)
講演2-2「名古屋大学キャンパスマスタープラン2010について(FM編)」
松岡利昌(名古屋大学 施設計画推進室准教授)
大学経営をどういう方向で導くのかというフレームワークの台本があり、PDCAサイクルを回しながらよりよいキャンパスを作っていこうという考え方。中心に統括マネジメントがありこれがエンジンであるが、民間ではファシリティマネージャーがいる。
老朽化建物が3キャンパスで350棟あるが、いかに大規模改修していくかが大きな論点。財源を確保しながら運営維持、補修点検、修繕するためにはベンチマーキングをしないといけない。財源に対して支払い金利の負担が大きくなり経営を逼迫しかねない。運営費交付金は年々削減。建物の管理に2つの項目、施設整備費、施設運営費がある。民間の金融機関や学校債の発行、土地を貸与して収入を得る、プロジェクトファイナンスなどのアプローチをしないといけない。
長期にわたって良好な環境を安定的に維持するために、戦略的な管理方針に基づく計画保全が必要。中長期30年の修繕計画、それを落とし込んだ5年計画、年次の計画まで落とし込まなくてはいけない。同時にデータベース化として施設管理システム、施設台帳を作って測定している。私大は維持管理費にお金をかけ、旧帝大、国立は水道光熱費、エネルギーコストが大きいなど、経営によってお金の掛け方が違う。財源を最適に配分していくための優先度判定を考えている。
ファシリティマネジメントを実際に推進していくために、経営の執行部隊がいて、そのなかにFM統括の実行部隊がいる。部局のFM担当と統括者がバランスを取ってコントロールする必要がある。同時に推進室、支援する部隊も必要。制度改革について3つあげると、基幹設備改修財源の確保、循環的な省エネ、利用面積に応じたスペースマネジメントである。
松岡利昌(名古屋大学 施設計画推進室准教授)
ディスカッション 15:10~17:00
テーマ:キャンパスマスタープランのあるべき姿とファシリティマネジメント(以下パネラー)
小林英嗣:北海道大学名誉教授、キャンパス計画に関する検討ワーキンググループ主査
上野 武:千葉大学教授、同キャンパス整備企画室長、上野藤井建築研究所主宰
飯田善彦:横浜国立大学教授、飯田善彦建築工房主宰
山崎雅雄(前掲)、藤井良一(前掲)
司会:恒川和久(前掲)、松岡利昌(前掲)(敬称略)
(小林)キャンパスマスタープランという概念が日本に定着していなかった10数年前、建築学会の中にキャンパス小委員会をつくった。平成22年はキャンパスマスタープランの元年になる、名古屋大学のマスタープランはその意味で先進的。キャンパスマスタープランの本意は、大学のミッションを社会、大学、構成員に明らかにすること。特色化、機能別分化が進んでいくときに個々の大学が国、地域、若い世代、企業にとっての責任を示すことがより必要。これまで、キャンパスはアカデミズムという目的がはっきりしたセクターと施設環境セクター、そして大学の経営・投資というセクターが別個に存在していたが、それらが極めて密接な関係にあることの自覚、三者を結び付けるマネジメント能力が重要。三者の総合的マネジメントの指針がキャンパスマスタープランであり、名古屋大学のキャンパスマスタープランはマネジメント概念に裏打ちされた新しい意味でのキャンパスマスタープランであり、フロントランナーとして期待している。
小林英嗣(北海道大学名誉教授、キャンパス計画に関する検討ワーキンググループ主査)
(上野)名古屋大学のマスタープランは「手引き」に組み込まれているエッセンスは100%近く盛り込まれ、過去のマスタープランを自己点検し、問題点をあぶり出し、それを構成員全体の共通認識として新しいものとしてまとめあげた点、その組織体系を評価する。 (手引きは)3つの「S」。safety, sustainability, strategy の組み立てで、各大学が個性的で戦略的なキャンパスマスタープランを作っていこうという中間まとめでありSustainabilityという言葉を深く考えることで大学の戦略になる。環境問題、社会の仕組み、経済性、3つで持続可能性。大学に置き換えると、経済は大学経営、社会貢献・社会的責任という意味でアカデミックプラン、これらが環境と一緒になってサスティナブルキャンパスが出来る。低炭素型都市、国際化戦略都市といった目的のために、大学キャンパスを「地域(都市)の縮小モデル」とし、そこまで考えて大学の計画にもう一度フィードバックするという考えがある。また、地方都市における大学の役割を踏まえ、自治体・企業と一緒に推進していく体制、たとえば名古屋大学のFM研究会とか、コンソーシアムといった体制作りが重要。
上野武(千葉大学教授、同キャンパス整備企画室長、上野藤井建築研究所主宰)
(飯田)現在マスタープランづくりの端緒にある。私鉄の駅が正門の逆側にできることによる人の流れの変化、不足していた学生の居場所等の具体的課題がある。名古屋大学キャンパスマスタープランは圧倒的。FMの部分は非常に専門的であり、一番大事な財政にどう踏み込んでいくのかは大きな問題。マスタープランが最初の概念であるが、それによってどう具体的なキャンパスが描けるかが一番難しく、今後作られるマスタープランと実際の建築をどう関連づけていくのかを考えなくてはならず、建築の質、環境の質をどうやって担保していくかが大きな課題である。大学という社会装置の変質、社会の変化のなかでマスタープランが威力を果たすのではないか。
飯田善彦(横浜国立大学教授、飯田善彦建築工房主宰)
(藤井)大学としてのミッションが複合的であるというのは分かるが、大学執行部にとって、どこにどうやってリソースを投入するかは、施設のポートフォリオ、学内全体のポートフォリオもあり、階層的であって難しい。今までは、予算がついたらそれから実行するという比較的受動的立場だったが、優先順位が時々刻々と変わっていく中で長期プランをどう作っていくか、今のところよくわかっていない。研究は短期的であるが、施設等は長期的という継続性の問題もある。実際のところ執行部ではそこまで至っていない。総長や理事は期限のある責任者、長い期間の責任を持てるかという問題もある。もう少し具体的に進める方法の示唆が欲しい。
(山崎)独立行政法人化前の閉鎖的状況を改善し国民へ説明する必要。きちんとミッションを説明して理解を貰う事が大事なステップであり、施設はそれをビジュアル化するものである。キャンパスマスタープランの公表により投資を呼び込み多用な財源を活用。また、大学の個性化による活性化の契機、大学の土台づくり、耐震化以外の点を評価しうる根拠としてキャンパスマスタープランが重要。今回の研究会を通じた再認識として、痛みを伴うスペースマネジメントだからこそ、理解と得るための「戦略」と「マネジメント」の両輪が必要。86大学全てがマスタープランをつくるのは実際難しいが、それを作らせることの意味合いについて小林先生に質問。
(小林)単独で大学間競争を勝ち抜くのが難しくなる中で、お互い協力し合う契機に。その際、コンソーシアムのマネジメントが問題になり、課題となる。その連携が知恵の出しどころ。
(山崎)補正予算でテーマを決めて施設をつくってきたがキャンパス全体をみると必ずしもいい環境ではない。改築から改修へシフトして進めてきたが、改修で対応できず改築もでてくる中で、キャンパスマスタープランをつくって課題を整理し、次に進むことが狙い。
(恒川)企業や自治体との連携というテーマへの話題転換。
(飯田)学生の設計課題において国大再整備計画を取り上げた際も「地域にどう開くか」というテーマが共通してあり、近接の地域、知の発信の両面が重要であり、(地域・企業が)大学の活動に興味を示して今まで無かったものが出てくる可能性がある。
(上野)結局は異なる組織の、思いを共有する個人の連携が重要。コストやスペースマネジメントは数字になるが、数字になりにくい「空間の質」をどう担保できるのかが問題となり、マスタープランをもとにした、発注・設計・使用・評価までの空間の質のマネジメントが課題。
(松岡)FM概念の中に「品質目標」があり、サービスレベルアグリーメントの視点が日本の大学に欠けており、課題となる。
(会場)大学のコンソーシアムを通じた、他大学を含めたマスタープランについて、また、実践していくうえでの失敗談を聞きたい。
(恒川)南山・中京・名城等地域の大学はそれぞれ明確な戦略があるためそれを尊重しつつ、都市の中のモデルとしては連携したい。
(松岡)失敗談として、民間的発想の提案をいくつもしてきたが、多くが却下された。
(小林)大学あるいは大学コンソーシアムが柱になって県、市町村、世界的な企業も巻き込んで一緒に総合特区を中京圏で立ち上げて、東アジアでチャレンジするとグローバルなレベルからも評価できる知の拠点の次の枠組みが出来る。そういう意味でも地域に開くことが必要。
(会場)PDCAを回していく中での手続きや質の担保のような話まで踏み込んで決めているのか。
(藤井)今回は大学としてオフィシャルにマスタープランが認められたという成果と、今後それをもとにポートフォリオ等の実施のしくみをつくることで前進したい。
(松岡)マスタープランに実施部隊の組織図を載せたことは成果であり、次のステップの入り口になる、そのための定期的会合をもっている。
(会場)キャンパスマスタープランとFMと並べたことが刺激的であるが、(FMの定義を再確認して)大学経営と施設を結び付ける評価項目、評価システムができないと難しい。
(松岡)「ファシリティマネジメント」という「施設マネジメント」より広い概念のメッセージを出したかった。
(まとめ)
(飯田)展示室や交流室など社会と結ぶことで大学のエンジンとなるような、今あるスペースの活用も求められる。
(上野)ポートフォリオの活用等で質も高い設計ができる仕組みを考えたい。
(小林)自治体が求めている創造性を大学が持つことが重要となる、市民も含めて居心地のいいもの、それが質にもつながる。それを担う「キャンパス建築」という形式があるのでは。
(山崎)マスタープランもアカデミックプランとリンクして、単に箱モノではなく、研究の活性化のため、また発信が必要。アイデアがあれば持ってきてほしい。
(藤井)大学は文化であり、(建築やキャンパスがそれを)どう実らせるかが重要。
(以上敬称略)
研究会全体進行・議事録要約:太幡英亮(名古屋大学 工学部施設整備推進室 助教)
前年度へ←
〒464-8601 名古屋市千種区不老町 TEL:052(789)5111(代表)
Copyright © 2010 Nagoya University All Rights Reserved.